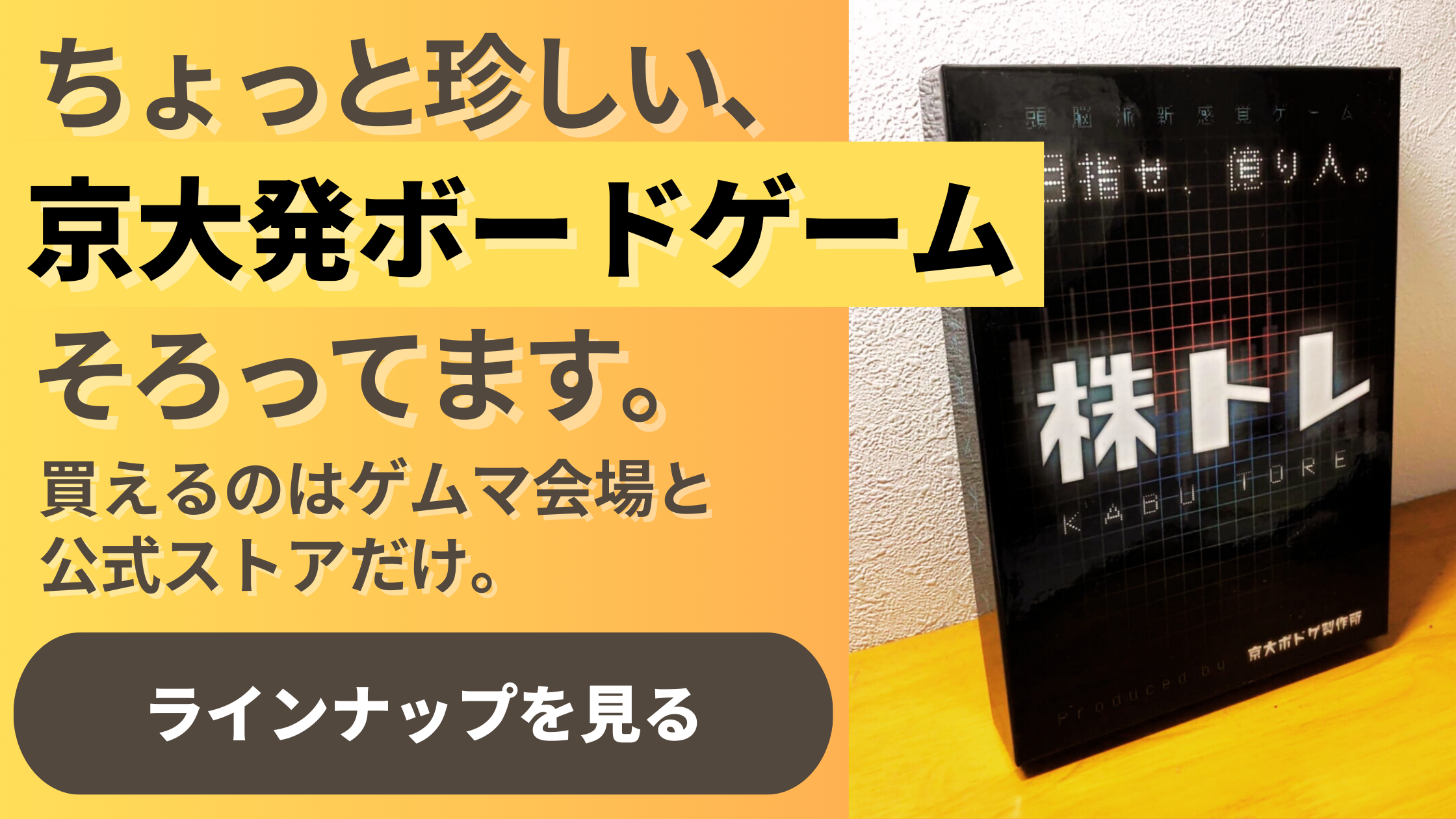小中学校や高校の休み時間や放課後に遊ぶなら、短時間で楽しめるカードゲームがぴったりですよね。この記事では、実際に販売されている定番カードゲームの中から、短時間で遊べてルールも覚えやすい、学校でおすすめの8作品を紹介します。
① ドブル(Dobble)
ドブルは、観察力と反射神経が試されるゲームです。55枚のカードにはそれぞれ8つのシンボルが描かれており、どの2枚を比べても必ず1つ共通の絵があります。その絵を最初に見つけて宣言した人がカードを獲得できます。
ルールが非常にシンプルで、1回のプレイは5分程度。低学年から高校生まで幅広く楽しめる点が魅力です。複数の遊び方ルールも用意されており、繰り返し遊んでも飽きにくい工夫がありますよ。
② はぁっていうゲーム
はぁっていうゲームは、声や表情で「感情」を表現して当て合うパーティー系ゲームです。例えば「はぁ」という言葉を「怒り」「照れ」「告白」など、カードに書かれたシチュエーションに沿って演じます。
他のプレイヤーは演じられた感情を推測する仕組みで、正解・不正解に関わらず盛り上がります。演劇遊びのような要素があり、グループの雰囲気を和ませたいときにおすすめです。
③ おばけキャッチ
おばけキャッチは、瞬時の判断が求められるスピード系ゲームです。カードには色や形が描かれており、机の中央にある5種類の木製コマの中から条件に合うものを素早く取ります。
反射神経が勝負のカギで、判断を間違えると笑いが起きるのも楽しいポイントです。テンポが速く、短い休み時間でも十分遊べますよ。
参考:おばけキャッチ
④ ナンジャモンジャ
ナンジャモンジャは、自由にキャラクターに名前をつけて遊ぶ記憶系カードゲームです。カードには12種類のユニークなキャラクターが描かれており、初めて出たときはプレイヤーが名前をつけ、再登場したらいち早くその名前を呼びます。
思い出せずに間違えたり、変わった名前で笑いが起きたりと、盛り上がりやすいのが特徴です。記憶力と瞬発力が自然に鍛えられる点も人気の理由です。
⑤ ito
itoは、数字カードを協力して順番に並べる会話型のゲームです。各プレイヤーは「1〜100」の数字カードを持ち、その数字を直接言わずに「お題」に沿った回答で表現します。
例えば「強い動物」というお題なら、数字が大きい人は「ライオン」、小さい人は「アリ」と表現します。お互いの意図をくみ取りながら順番をそろえる過程で自然と会話が弾むのが魅力です。
参考:ito – ArclightGames Official
⑥ ボブジテン
ボブジテンは、カタカナ語を日本語だけで説明するユニークなゲームです。例えば「アイスクリーム」を「冷たい甘い食べ物」と言い換えるなど、語彙力と発想力が求められます。
カタカナ禁止という制約が笑いを生み、説明の工夫次第で盛り上がります。学校で遊べば、日本語力を伸ばす学習的な一面も期待できますよね。
参考:ボブジテン〈TUKAPON〉|メーカー,TUKAPON|ClaGlaウェブショップ|ボードゲームメーカーの直販店
⑦ カタカナーシ
カタカナーシは、「カタカナ語を禁止して説明する」ゲームです。カードに書かれたお題を、ジェスチャーや別の言葉で工夫して伝えます。
短時間で1ラウンドが終わるため、スキマ時間でも遊びやすいのが特徴です。誰でもすぐに参加できるので、大人数で楽しむのにも向いています。
⑧ ワードバスケット
ワードバスケットは、しりとりをスピードアップしたような言葉遊びゲームです!場に出ている文字で始まる言葉を考え、手札の文字で終わるようにカードを出します。
テンポが早くなるにつれて緊張感が増し、語彙力と瞬発力が鍛えられます。慣れてくると白熱した展開になり、クラス全体で盛り上がれる定番のカードゲームですよ。
参考:ワードバスケット
ボドゲを作っています
様々なオリジナルゲームを企画・開発。








-1024x726.jpg)