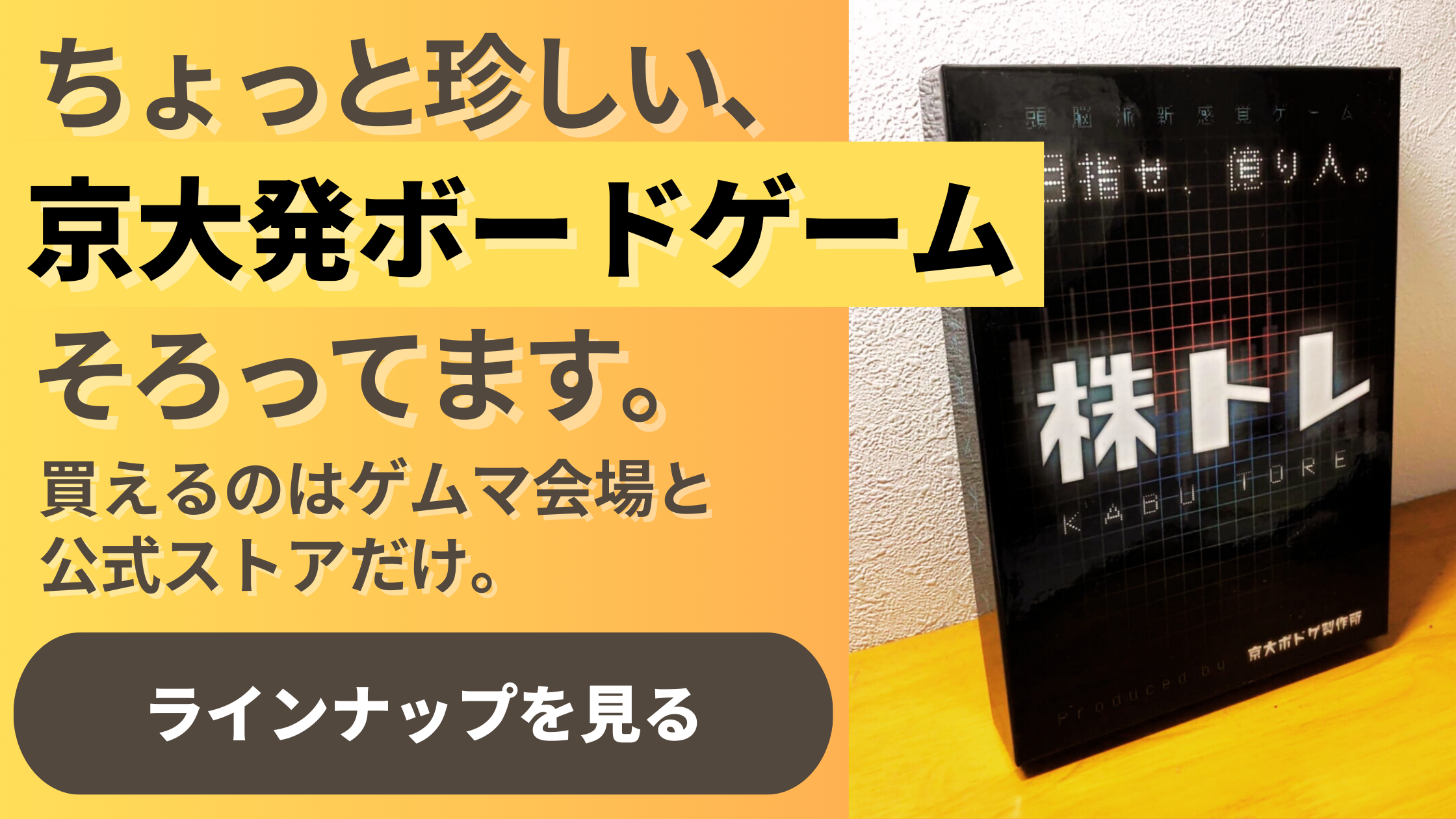理科の世界には、面白い法則や発見がたくさんあります。しかし、子どもにとって学校の授業だけではなかなか興味を持ちにくいこともあるでしょう。そんなときにおすすめなのが、理科を楽しく学べるボードゲームです!
ボードゲームなら、遊びを通じて手軽に理科の知識を深められます。本記事では、理科に興味を持ち始めた子どもや、これから理科を勉強するという方におすすめのボードゲームを7つご紹介します。
科学に関するボードゲームは下記の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ併せてご覧ください。
ボードゲームで理科を学ぶメリット
ボードゲームを活用して理科を学ぶと、以下のようなメリットがあります。
楽しみながら学べる
ボードゲームを遊びながら自然と学ぶことで、苦手意識を持たずに理科という学問に馴染めます。一人で勉強するのではなく、家族や友人と一緒にコミュニケーションを取りながら理科に触れられるため、興味を持つきっかけになりやすいでしょう。
学習の理解を助けてくれる
ボードゲームには、トークンやカードで理科の概念をビジュアル化して再現してくれているものが多くあります。これらのゲームを遊ぶ中で、抽象的な理論を感覚的に理解しやすくなる効果もあるでしょう。
論理的思考力が育つ
理科系のボードゲームにはプレイヤーの行動を読んだり、資源を管理したりする戦略的な思考が求められるものも多いです。科学に触れるというだけでなく、学びに必要な論理的思考力が同時に鍛えられます。
理科系のボードゲーム・カードゲームおすすめ7選!
ユーリカ・モーメント

プレイヤーが科学者となり、資源トークンを集めながら、科学の発明を進めていくボードゲームです。ゲームでは、エネルギー、技術工学、生物化学、情報伝達、社会システムの5つの分野の資源を管理し、発明カードを獲得して文明を発展させていきます。科学の歴史を追体験しながら、どのように科学が発展してきたのかを学べる構成になっています。
参考ページ:
熱力学ワーカーズ
プレイヤーは「系」と呼ばれるコマをPVグラフ(圧力-体積グラフ)上で移動させ、エネルギー(ジュール)を獲得するゲームです。等圧変化や等積変化といった熱力学の概念を活用しながら戦略を立て、最終的に最も多くのエネルギーを集めたプレイヤーが勝者となります。熱エネルギーの移動や保存の仕組みを体感的に学べるため、物理の理解が深まります。
Dr.STONE ボードゲーム 千空と文明の灯
プレイヤーは『Dr.STONE』のキャラクターとなり、協力しながら科学技術を駆使して文明を発展させるボードゲームです。各キャラクターにはアクションポイント(AP)があり、移動や探索、素材の変換などを行いながら制限ラウンド内に目的のアイテムを作り出すことを目指します。資源管理や戦略的思考が求められるため、ゲームを通じて科学的な思考力を鍛えることができます。
参考:Dr.STONE ボードゲーム 千空と文明の灯 – ArclightGames Official
原子モデルカードゲーム
原子の構造や元素の結合を学ぶために作られたカードゲームです。各カードには元素記号と原子価が記載されており、プレイヤーはそれらを組み合わせて化合物を作ります。作成した化合物の安定性や種類によって得点が決まり、最も多くの得点を獲得したプレイヤーが勝者となります。遊びながら周期表の法則や分子構造を理解できるため、化学の基礎学習に役立ちます。
参考:原子モデルカードゲーム
ドクターエウレカ
試験管に入ったボールを、決められたルールに従って移し替えながら、指定された順番に並べるアクションパズルゲームです。プレイヤーはピンセットなどの道具を使わずに、手早く正確にボールを移動させる必要があり、手先の器用さと素早い判断力が試されます。パズルの解法を考えながら、化学実験のプロセスを体感できるユニークなゲームです。
参考:ドクターエウレカ 日本語版 – テンデイズゲームズ -TendaysGames-
ニュートン
プレイヤーは18世紀の科学者となり、研究や旅を通じて知識を深め、名声を高めることを目指す戦略的なボードゲームです。手札のカードをプレイして、研究、講義、技術発展などのアクションを実行し、最終的な勝利点を競います。プレイを重ねるごとにアクションが強化され、科学の発展を疑似体験できるゲームです。
参考:ニュートン 偉大なる発見同梱版 日本語版 – テンデイズゲームズ -TendaysGames-
テラフォーミング・マーズ
プレイヤーは企業のリーダーとして、火星の環境を地球化(テラフォーミング)し、人類が定住できるようにすることを目指すゲームです。酸素濃度を上げ、気温を調整し、水源を確保しながら、火星の地形を変えていきます。各企業ごとに異なる能力を活かしながら、資源を管理し、プロジェクトを進めて勝利点を競います。地球科学や天文学、生態学の要素が組み込まれており、戦略性と科学の知識が融合した奥深いゲームです。
参考:テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 – ArclightGames Official
ボドゲを作っています
様々なオリジナルゲームを企画・開発。

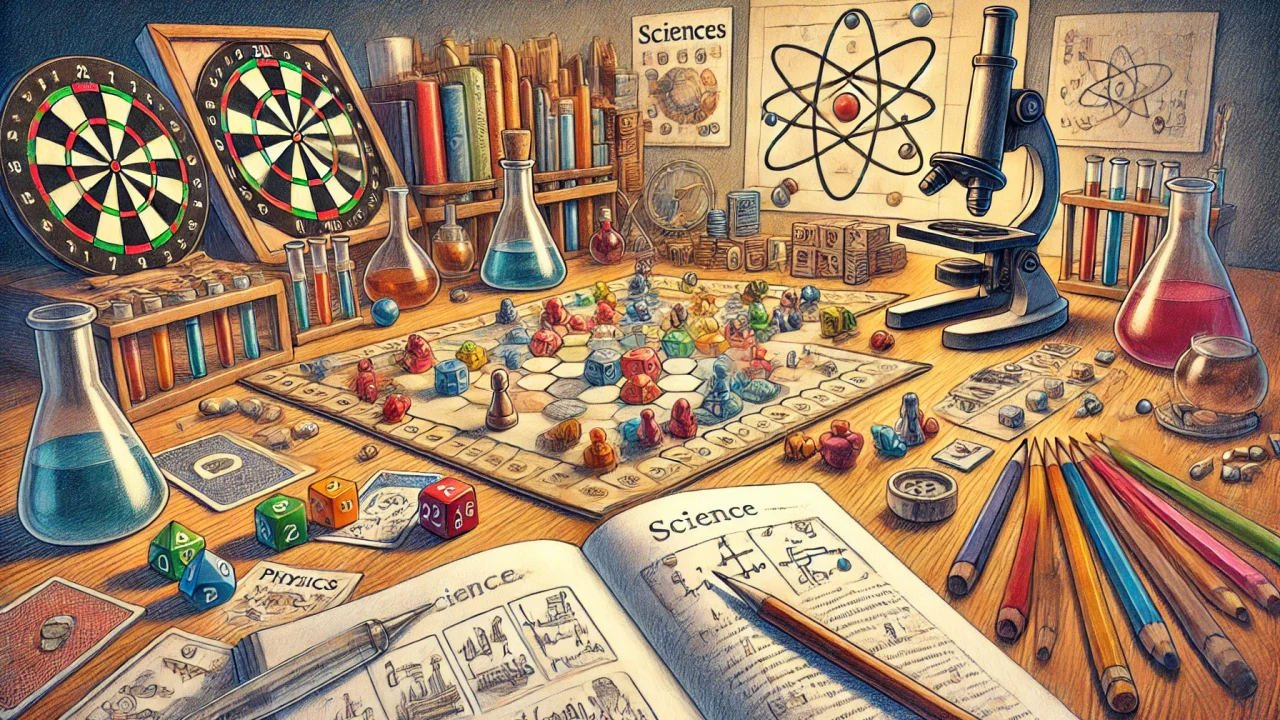


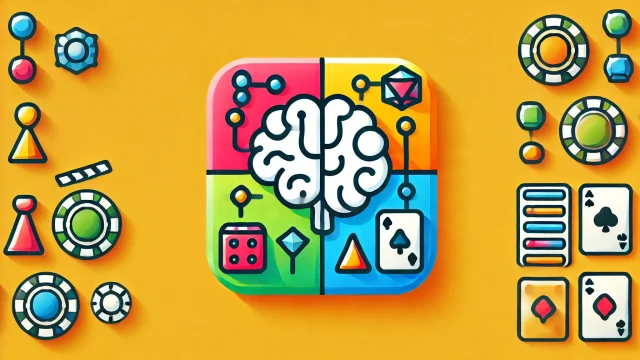





-1024x726.jpg)